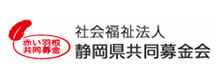重症心身障害児者の摂食嚥下障害に対する取り組み
食事は私たち人間にとって活力を与えてくれる源であると同時に、さまざまな味わいを堪能できる大きな楽しみでもあります。それは障害児にとっても同様で、一日の生活のうち3回も経験する食事の時間が苦痛なく楽しいものであってほしいと願います。
しかしこの2年半の間で「つばさ静岡」入所者たちに誤嚥や窒息などの嚥下障害による問題が想像以上に生じてきている実態を目の当たりにし、重症児にとって嚥下障害は進行性の病態であることを痛感させられました。
けれども嚥下障害が進行したからといってすぐに経口からの食事をあきらめることに対しては疑問を抱きました。
本当にもう限界なのか?その前に私たちがやり残したことはないのか、まだ試してみるべきことがあるのではないか?できることなら1日でも長く安全に苦痛なく経口で食事を摂取させてあげたい。
現に誤嚥性肺炎を繰り返していながらも食事がでてくると目を輝かせて喜ぶ利用者の姿をみて、奮い立たされこの難題に「つばさ静岡摂食チーム」(医師、OT、PT、栄養士、調理師、現場スタッフ)で取り組むことにしました。
取り組み後、発熱の頻度が減少した、経口摂取量が十分量摂取でき体重が増えた、食事中のむせ、ぜこつき、筋緊張が減少したなど臨床上ある程度手ごたえを感じております。
重症児の嚥下障害への挑戦はまだまだ始まったばかりで、長期的な観点からは検討しておらず、あくまでも「目先の改善」にすぎないかもしれません。
しかし経口摂取中止寸前だった人が、対応の変化により継続できた例を少なからず経験したため、私たちの経験が少しでも在宅の皆様にもお役に立てればと思い、その取り組みについてこれからシリーズでお伝えしたいと思います。
- 医務部長 浅野一恵
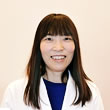
【重症児の摂食リハビリに対する私たちの考え方】
今回は重症児の嚥下障害に対する私たちの考え方についてお話したいと思います。
私たちが対象としている重症児の方は学齢期後半を過ぎた寝たきり~座位保持可能ぐらいの運動機能の方がほとんどです。そのためここでは、10代後半の運動障害の重い方を中心に話を進めていきたいと思います。
- Ⅰ.重症児の嚥下障害の病態
-
はじめに重症児の嚥下障害の病態を考えて見ましょう。 高齢者の嚥下障害と比較し、重症児の嚥下障害は非常に複雑な要素が絡み合っており、100人重症児がいれば100通りの嚥下障害のパターンがあるといっても過言ではないでしょう。
そのため一概に「重症児の嚥下障害」とひとまとめにして考えるのは危険なのです。
以下に主な嚥下障害の要素を挙げます。- 1.生まれつきの脳病変による嚥下運動障害
- 2.未熟性の残存による嚥下機能獲得不全
- 3.限定された運動パターンでの代償
- 4.加齢による構造・機能変化
- 5.呼吸障害、消化管障害、筋緊張による嚥下障害の修飾
生まれつきの広汎な大脳障害によって嚥下協調運動障害が生下時より存在します。 脳幹障害により嚥下反射が減弱したり、大脳障害により舌や顎、咽頭筋の協調運動障害を生じるため、一連の嚥下運動がスムーズに行かず、嚥下と気道防御のタイミングがずれたり、嚥下力の減弱をきたします。 しかし原始反射や未熟な機能(吸啜、舌の前後運動など)を使って代償することで哺乳、摂食がある程度可能です。 またアテトーゼの方たちは比較的自分でコントロールがつけやすい舌を過剰に動かすことによって機能を代償しようとしている方もいます。離乳期を過ぎると介護者はより硬い食形態を与えるようになります。 それに対し運動障害の明らかな重症児は、発達的に未熟な段階で停滞することが多く、有効な咀嚼機能を獲得することができないため、丸飲み込みや舌突出嚥下などの代償機能で対処するしかありません。 しかし小学校~中学校卒業ぐらいから構造的、機能的な加齢の変化-すなわち喉頭が広くなる、嚥下反射が遅くなる、嚥下力が低下する、気道防御弁の機能が低下するなど-が生じてきます。さらに呼吸障害や消化管障害、筋緊張の亢進などが加わり、嚥下障害に悪影響を及ぼしてきます。その結果代償機能は破綻し、窒息、誤嚥などの臨床的な問題が生じてきます。 このように重症児の嚥下障害は運動障害の程度、機能獲得段階、代償機能、加齢現象、全身の合併症など多くの要素が関係しあっています。そのため食事姿勢を考えるにしても、呼吸機能、消化管機能、筋緊張が安定し、代償機能が有効に働き、かつ誤嚥しにくい姿勢を検討していく必要があります。
- Ⅱ.私たちのとったアプローチ方法-客観的評価-
- 今までお話してきましたように重症児の嚥下障害はさまざまな要素が絡み合っており、パターンは何百通りあると思われます。そのため対応は個別的に考える必要があります。 対応を考えるうえで大切なのは嚥下障害が臨床的にどんな問題を引き起こしているかを客観的に評価することです。 その評価方法には大きく2つ-縦断的(経時的な変化)な評価と、横断的(現時点での機能)な評価-の両者が必要になってくると思われます。 例えば縦断的評価では今まで食事中のむせがあった人が、発熱をみとめるようになり、さらに誤嚥性肺炎を繰り返すようになった場合と、いままでむせなどの誤嚥の兆候のなかった人がたまたま嘔吐をきっかけに誤嚥性肺炎になった場合では対応が異なります。 また横断的な評価では嚥下造影を中心とした嚥下機能評価(嚥下力、嚥下反射遅延、誤嚥の量やタイミングが姿勢や食形態でどう変化するか)のほか、誤嚥物を排出するための咳嗽能力、免疫力、呼吸機能などを総合的にかつ客観的に評価する必要があると考えます。(縦断的、横断的評価に関しては次回以降詳しくお話しする予定です) それら縦断的評価と横断的評価を組み合わせて、その人の嚥下障害は許容範囲なのか、許容範囲を超えてしまっているのかを判断し、対応を分けていくことが必要と考えます。 そして介入後の評価もあくまでも臨床的に改善したかどうか-むせが減った、肺炎の頻度が減った、食事摂取量が増えた、食事時間が短縮した、体重が増加した等-を重視しました。
- Ⅲ.介入のスタンス
- もうひとつ大切なことはどういうスタンスで介入するかです。 この際私たちがとった立場は必ずしも正常な機能をお手本にしないということです。 特に嚥下障害が許容範囲を超えつつある人に対しては、「安全に十分量が経口から摂取できること」が一番の目的で、「正常に食べる機能を獲得する」ということが目的とはならないでしょう。 私たちが対象とする運動障害が重度な重症児はたとえどんなに訓練しても正常な摂食機能(特に捕食、咀嚼などの口腔機能)を獲得することは困難と考えます。 現に今まで全量経口摂食してきた重症児たちは何らかの代償機能を利用し摂食しているのです。 その代償機能をある程度許容し、利用するという考え方を私たちはとりました。 たとえば丸飲み込みは敵視されることが多いですが、気道防御弁が働かなくなり誤嚥するようになった場合、実は有利かもしれません。中途半端な咀嚼で細かく砕いてしまわれると、バラけてしまった粒を誤嚥してしまい、ひどい肺炎を繰り返してしまうでしょうが、適切にやわらかくまとまった食形態を丸飲みすることで誤嚥も窒息もせず済みます。 吸啜という動作も嫌われがちですが、利点もたくさんあり、口唇閉鎖ができる、嚥下力を口腔陰圧でカバーできる、流速をコントロールできるなどがこの動作により可能かもしれません。 ですから私たちの目指したのは、「現時点で持っている機能を最大限に生かせるような食環境づくりを目指す」というものです。適切な食環境づくりとはすなわち適切な「食形態」と「食事姿勢」、「介助方法」を個別に検討することです。 次回以降は客観的な評価法、食形態、食事姿勢、介助方法、排痰方法、医療介入などについて具体的に説明する予定です。皆様からのご感想、ご批判お待ちしております。
- 社会福祉法人 小羊学園 つばさ静岡
- 〒420-0805 静岡市葵区城北117
- Tel.054-249-2830 Fax.054-249-2831
- e-mail:tubasa-szok@wind.tnc.ne.jp
- アグネス静岡(相談支援事務所)
- >>詳細及び連絡先はこちら